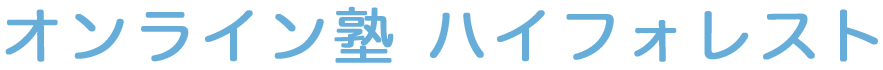勉強しなきゃ…でもスマホが気になる。そんな時の対処法をご紹介!

スマホをいじっていたら、30分があっという間に過ぎていた。勉強しなきゃと頭ではわかっているのにやる気がついてこない。そんな時、たった5分で勉強のスイッチを入れる“最初の一歩”をご存知ですか?
手元にあるスマホの誘惑は強烈で、「気づいたら時間が溶けていた…」なんて経験、誰にでもありますよね。
保護者の皆さんも、お子さんがスマホばかり触っていて勉強が進まない様子に、やきもきしているかもしれません。
このブログでは、そんな皆さんの悩みに寄り添いながら、スマホと上手に付き合いながら勉強を充実させるための具体的なヒントをお伝えします。
「わかっているけどできない」の正体

私たちは、「やるべきこと」と「やりたいこと」の間で常に揺れ動いています。勉強は「やるべきこと」の代表例ですが、スマホを見ることは「やりたいこと」の筆頭ですよね。この葛藤は、実は人間の脳の仕組みと深く関係しています。
脳には、「短期的な快楽を求める部分」と「長期的な目標達成を目指す部分」があります。スマホを触ることは、すぐに楽しいという「短期的な快楽」が得られるため、脳はそちらを優先しがちです。一方、勉強はすぐに結果が見えるわけではなく、「長期的な目標達成」のためにコツコツと努力が必要です。このため、脳は短期的な快楽に流れやすく、「わかっているけどできない」という状況が生まれてしまうのです。
しかし、これは決してあなたが弱いからではありません。人間の自然な反応なのです。だからこそ、この脳の仕組みを理解し、それに逆らわずに、むしろ味方につける工夫が必要になります。
5分で勉強モードに切り替える“最初の一歩”

「よし、今から3時間勉強するぞ!」と意気込んでも、なかなかスタートできないことってありますよね。これは、脳にとって「3時間勉強する」というハードルが高すぎるからです。そこで効果的なのが、「たった5分だけ」という魔法の呪文です。
1. 目標を極限まで小さくする
「たった5分だけ、教科書を読む」「たった5分だけ、問題集の1問だけ解く」「たった5分だけ、単語を5個覚える」など、どんなに小さなことでも構いません。重要なのは、「これならできる」と思えるくらいハードルを下げることです。
2. スマホを遠ざける
「たった5分」の間だけでも、スマホは別の部屋に置くか、電源を切るなどして視界に入らない場所に置きましょう。通知が来ないように設定するのも有効です。
3. ストップウォッチで計る
実際に5分間集中できたかを確認するために、タイマーやストップウォッチを使ってみましょう。5分という時間はあっという間ですが、集中して取り組むことで、脳は「やればできる」という成功体験を認識し始めます。
この「たった5分」の積み重ねが、やがて10分、15分と集中できる時間を伸ばしていくきっかけになります。脳は成功体験を記憶し、次の行動へのハードルを下げてくれるのです。
「計画の力」と「メリハリ」

勉強時間を有効活用するためには、漠然と「勉強しよう」と考えるのではなく、具体的な計画を立てることが重要です。
1. 「見える化」する計画作り
• 長期目標の設定: 何を達成したいのか、大きな目標を立てましょう。例えば、「苦手な数学の単元を克服する」「〇〇の資格の勉強を進める」などです。
• 中期目標への分解: 長期目標を達成するために、1週間単位で何をすべきかを決めます。
• 短期目標への落とし込み: 1日単位、あるいは午前・午後で何をどこまでやるかを具体的に決めます。
紙のスケジュール帳やカレンダーに書き出すことで、自分のやるべきことが「見える化」され、達成感が得やすくなります。毎日寝る前に翌日の計画を立てる習慣をつけるのも良いでしょう。
2. 「ご褒美」を設定する
勉強を頑張った後の「ご褒美」を設定することは、モチベーション維持に非常に効果的です。「〇〇ページまで進んだら、30分スマホを触る」「この単元が終わったら、友達とゲームする」など、自分にとって魅力的なご褒美を用意しましょう。ただし、ご褒美はあくまでも「達成した後」であり、勉強の途中でご褒美に手が伸びないよう注意が必要です。
3. 「休息」と「気分転換」も計画に入れる
勉強と休息はセットです。長時間ぶっ通しで勉強するよりも、適度な休憩を挟んだ方が集中力は持続します。
• ポモドーロ・テクニック: 25分勉強+5分休憩を繰り返す方法です。集中力を持続させやすいとされています。
• アクティブレスト: 休憩時間には、スマホを触るのではなく、軽いストレッチをしたり、飲み物を取りに行ったり、少し散歩に出かけるなど、体を動かすことで気分転換を図りましょう。
スマホとの賢い付き合い方

スマホは私たちの生活に欠かせないツールですが、使い方を間違えると勉強の妨げになります。賢い付き合い方とはどのようなものでしょうか?
1. 通知オフの徹底
SNSやゲームの通知は、集中力を著しく阻害します。
勉強中は、必要な通知以外はすべてオフにするか、機内モードにするなどして、通知に邪魔されない環境を作りましょう。
2. 使用時間の制限アプリの活用
スマホの使用時間を制限するアプリや、特定のアプリの使用を制限する機能などを活用するのも有効です。
物理的に触れないようにするだけでなく、アプリの力も借りて「強制的に」スマホから距離を置く時間を作りましょう。
3. 「デジタルデトックス」のすすめ
週に一度、あるいは一日のうち数時間だけでも、完全にスマホから離れる時間を作ってみましょう。
デジタルデトックスは、脳を休ませ、集中力を高める効果があります。
その時間を使って、読書をしたり、趣味に没頭したり、家族と過ごしたりするのも良いでしょう。
保護者の皆さんへ:温かいサポートの力

お子さんが勉強に集中できるよう、保護者の皆さんのサポートは不可欠です。
サポートの具体例は次の通りです。
• プレッシャーを与えすぎない: 「勉強しなさい」と口うるさく言うよりも、「何か困っていることはない?」と優しく声をかけ、お子さんの話に耳を傾ける姿勢が大切です。
• 環境を整える: 集中できる静かな場所を用意したり、必要な参考書や文房具を揃えたりと、お子さんが勉強しやすい環境を整えてあげましょう。
• 頑張りを認める: 小さなことでも、お子さんの頑張りや成長を具体的に褒めてあげましょう。達成感を共有することで、お子さんのモチベーションは大きく高まります。
• スマホ利用のルールを一緒に決める: 一方的にルールを押し付けるのではなく、お子さんと一緒にスマホの使用時間や場所、ルールを話し合い、合意の上で決めることが重要です。
【まとめ】
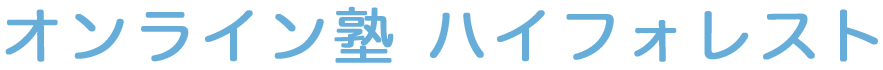
如何でしたでしょうか?
スマホとの付き合い方を見直し、自分なりの「集中モード」の入り方を見つけることで、あなたの成長を大きく後押ししてくれるはずです。
最初の一歩は、いつも「たった5分」から。さあ、今すぐスマホを置いて、小さな一歩を踏み出してみませんか?
当塾は【元高校教師の授業が受けられる】【完全マンツーマン指導】の塾です。
実際に学校現場で教えた経験のある講師が授業を行うため、様々な生徒さんに合わせた授業を展開します。
また、完全マンツーマン指導なので、他の生徒さんの進行度合いを気にすることなく質問が出来ます。
豊富な知識を持った教師が対応しますので、授業以外のことでも気軽に質問が出来ます!
当塾の指導実績は以下の通りです!
★中学3年生 1か月で地区実力テスト総合点が82点アップ!
★中学2年生 3か月で数学の学年順位が70番アップ!
★浪人生 3か月で国語の模試が98点アップ!
★志望校100%合格!
無料体験も受け付けていますので、この記事を読んで塾に少しでも興味を持った方は是非お申し込みください!